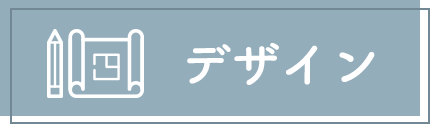三重で注文住宅を建てたら必要になる費用・土地の相場
注文住宅の費用の相場や、年収別の予算相場、受けられる軽減措置についてまとめています。
注文住宅を建てる際にかかる費用
土地がある場合とない場合の費用相場の違い
注文住宅を建てるために必要な費用は、土地がある場合とない場合で、相場も異なります。すでに土地をもっていて、注文住宅を建てる場合の費用の相場は約3,072万円、土地も購入して注文住宅を建てる場合の相場は約4,176万円といわれています。
年収別の予算相場
注文住宅にかけられる費用は、年収によって異なります。
住宅の購入予算は「年収×年収倍率+自己資金-諸費用」で算出できます。ちなみに、年収倍率とは、住宅の購入価格と年収の比率のこと。年収倍率が低いほど住宅が買いやすく、高いほど買いにくいといわれています。参考までに年収倍率を5倍として、また、自己資金を年収1年分、諸費用を物件の5%として、年収別の予算を計算してみましょう。
- 年収400万円
400万円×5+400万円-120万円=2,280万円 - 年収600万円
600万円×5+600万円-180万円=3,420万円
ここ最近の年収倍率は、拡大傾向にあるため、注文住宅の予算相場は、この数字よりも高くなると考えられます。
注文住宅の予算の内訳
注文住宅を建てる際の、予算の内訳としては、基礎や躯体、屋根、内装、電気工事、各種設備など、建物自体にかかる費用が全体の70%、外構工事、照明などの付帯工事にかかる費用が20%、登記費用や各種保険、引越しなどの諸費用が10%だといわれています。
住宅の取得に対する軽減
不動産を取得した際、「不動産取得税」という税金が課せられます。住宅の場合、その税率は3%とされていますが、新築住宅を取得した際には、軽減措置を受けることができます。
新築住宅の場合、住宅の延べ床面積が50m2以上、240m2以下であれば軽減措置が適用され、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。つまり、不動産取得税額は(固定資産税評価額-1,200万円)×3%となります。
住宅用土地の取得に対する軽減
新築住宅用の土地においても、軽減措置があります。
- 45,000円(税額45,000未満の場合にはその金額)
- その土地の1平方メートルあたりの価格×1/2×住宅の床面積(最大200m2まで)×3%
土地の場合は、1か2の、どちらか金額の大きいほうの金額が、税金から減額されます。この軽減措置を受けるためには、新築した住宅が、新築住宅の軽減措置を受けるための要件に該当している以外に、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を新築して、住宅が新築されるまで、その土地を所有していること
- 住宅を新築して1年以内に、その住宅を新築した人が、その住宅の土地を取得していること
- 住宅が新築される前に、取得した土地を第三者に譲り渡した場合は、土地を取得してから3年以内に、その第三者がその土地に住宅を新築していること
詳しくは、物件所在地の管轄となる、県税事務所に問い合わせてみてください。
本体工事費
建物本体の工事にかかる費用です。仮設から基礎工事に木材の加工など、構造や仕上げ工事が建築工事費用に含まれます。依頼する業者にもよりますが、標準仕様の部分がオプション仕様となっている可能性も考慮しておきましょう。
基礎工事以外にもタイルやガラスの取り付け作業に加え、防腐処理の費用も本体工事費に含まれます。他にもさまざまな費用が本体工事費に含まれまるので、どれだけの工事を本体工事費とするのか、複数の業者に聞いてみて比較するのも良いでしょう。業者の中には資金繰りについての相談に対応しているところもあるので、予算やローンの計画が決まらない時は一度細かく聞いてみることが大切です。
一般的に、この本体工事費が家造りの7~8割を占めます。
付帯工事費
建物に付帯する各種設備工事が付帯工事費です。現場仕事にかかる費用で、現場管理に必要な費用として事務・通信・運搬・監督の人件費なども含まれます。
まず、作業にあたり、いろいろと仮設が必要です。道路清掃用や工事用の水を確保する仮設水道費、工事現場で使用する電動工具。照明用の電源を設けるための仮設電気費や作業員用の仮設トイレなどが該当します。
また、それに付随して地盤の強さを測るための地盤調査費、電線を道路から引き込む電気工事なども付帯工事費です。指定された専門会社が行うガス工事、給排水管を建物に引き込む屋外給排水工事、産業廃棄物処理費なども同様の諸経費として扱われます。
別途工事費
敷地の条件のように、不確定要素の項目や施主様の方で希望された項目など、本体工事費に含まない費用が該当します。例えば、建替えを行う場合や購入した土地にまだ建物が建っている場合には、別途で解体するための費用が必要です。
解体工事は、足場を組んで建物を解体する、周囲にホコリや音などの迷惑をかけないためにシート養生しなければいけません。また、家本体だけでなく庭に植えてある樹木や塀、カーポート(屋根の柱だけの車庫)や物置を移設したり処分したりするための費用も含まれます。
地盤補強工事費
家を建てたい場所の地盤が沈下する恐れがある場合、地盤補強工事をしてもらいましょう。地盤補強が必要か、必要であれば具体的にどのような手法で補強するかを検討した上で見積りを立ててもらえます。地盤の状態にもよって、地表面にセメント系の材料を混ぜ合わせて固める地盤改良工事や、固い地盤に達するまで深く杭を打ちこむ工事で対応。地盤沈下のリスクを抑えます。
工事の種類や補強する深さによって費用は変動しますが、100~200万ほどの予算は用意しておくべきです。予算を抑えたいなら、地盤改良が必要かどうかも視野に入れて土地を選んだほうが良いでしょう。
エクステリア工事費
外構や庭などのエクステリア工事関連費用もあります。門の両わきに立てる柱や扉にフェンス、車庫などにかかる費用はもちろん、造園するための費用も必要です。住宅の施工が完了してから施工すると、家造りを依頼した建築会社でも別の契約を結ぶ場合もあります。
他にも照明器具費やエアコン機器などの空調設備工事費、カーテン等の内装関係費用のように細かな費用がかかるのがポイントです。全体的な金額を把握しておけば、予算内でどのような家を建てられるのかをイメージしやすくなるでしょう。
借入にかかる費用
銀行の住宅ローンや住宅支援機構などから融資を受ける際には、団体信用生命保険への加入が必要となります。これは返済途中に加入者が亡くなる、もしくは高度の障害を負ってしまった際、支払うことが難しくなった時のための保険です。団体信用生命保険に入っておけば、保険金によって住宅ローンの残額が返済される仕組みで対応してもらえます。
民間金融機関のローンでは、この団体信用生命保険への加入が融資の条件となっている場合がほとんどです。また、長期の固定金利ローンであるフラット35の場合は、加入が融資の条件にはなっていません。ただし、実際にはほとんどの方が加入されています。
保証料
住宅ローンを借りる際、月々の返済だけでなくローン保証会社に支払う保証料も発生します。連帯保証人を立てられない場合、保証会社がローンの残債を支払ってくれるというシステムです。この場合、資金の返済先は保証会社に変更となります。支払い義務は継続されるので、覚えておきましょう。
また、火災保険への加入も、融資を受ける場合には必須となります。保険料は建物の構造・所在地・保険期間などで異なるので、ある程度調べておいたほうがスムーズに手続きを進められるでしょう。地震保険の保険料も同様です。
ローン借入れの金銭消費貸借契約時には、融資事務手数料が発生します。また、融資の抵当権を敷地・建物に設定する場合だと抵当権設定登記費用が必要です。
融資実行よりも建物の引渡しが先行する場合、公的融資の場合であればつなぎ融資によって融資実行までの期間に銀行から借入れができます。
注意点として、財形住宅融資などの公的融資では、建物の引渡しが済み建物が借入者の名義になるまで融資の実行ができません。銀行からのつなぎ融資で建築費の支払いに当てることで、住宅の引き渡しが完了となります。
その他
設計契約や工事請負契約・金銭消費貸借契約などの契約書には印紙税がかかります。地鎮祭に掛かる費用は、神主への謝礼と供物代が必要です。上棟式を行う場合にかかる費用として、通常は家づくりに携わる方々へのご祝儀や式の際の飲食代を用意します。着工前の近隣へのあいさつ廻りや工事中の職人さんへのもてなしにかかる費用についても、忘れず予算に組みこんでおきましょう。
建て替えの場合は仮住まいが必要となるので、家賃が必要となります。また、引越しの費用(建替えの場合は2回必要)も併せて用意しておかなければいけません。家具などが多い場合、仮置き費(トランクルーム)もかかります。不必要なものがあれば、事前に処分したり売却したりすることで荷物や家具を減らしておくのが良いでしょう。
その他の費用として、水道を引くときに必要となる「水道加入金」が発生する場合があります。自治体によって金額は異なり、また不要な自治体もあるので確認が必要です。
三重県の土地相場
土地の平均価格
三重県の公示地価は平均4万5007円/m2(2019年)、坪単価は平均14万8784円/坪であり、全国順位は32位/47都道府県となっています。
基準地価は平均3万7795円/m2(2019年)、坪単価では平均12万4944円/坪で、全国順位は3位上がった29位/47都道府県です。
三重県内においての基準地価は、4〜6万円/m2で高額、1万円/m2付近で定額と位置付けられます。
市町村で異なる地価
四日市市
- 地価平均:6万5230円/m2
- 21万5638円/坪
四日市市の基準地価平均6万5230円/m2(2019年)、坪単価平均21万5638円/坪は全国順位は290位です。前年からの変動率+0.34%は全国順位は321位です。
四日市市と同じ鉄道路線内で土地相場を比較すると、四日市市は近鉄名古屋線沿線の平均地価26万0703円/m2、JR関西本線沿線の平均地価24万0403円/m2を下回っています。近鉄名古屋線、JR関西本線の駅へ距離が短いほど四日市市内の基準点地価は高い傾向にあるようです。
全長9mのからくり人形「大入道」が登場する「大四日市まつり」やユネスコ無形文化遺産に登録されている「鳥出神社の鯨船行事」のように、伝統的な祭が行なわれている四日市市。特産品には伊勢茶や地酒、とんてきがあります。
桑名市
- 地価平均:6万4395円/m2
- 坪単価平均:21万2876円/坪
桑名市の基準地価平均6万4395円/m2(2019年)、坪単価平均21万2876円/坪は全国順位は293位です。前年からの変動率−0.41%は全国順位は583位となっています。
桑名市と同じ鉄道路線内で土地相場を比較すると、桑名市は近鉄名古屋線沿線の平均地価26万0703円/m2、JR関西本線沿線の平均地価24万0403円/m2を下回っています。近鉄名古屋線、JR関西本線の駅へ距離が短いほど桑名市内の基準点地価は高い傾向にあります。
朝日町
- 地価平均:4万8566円/m2
- 坪単価平均:16万0550円/坪
朝日町の基準地価平均4万8566円/m2(2019年)、坪単価平均16万0550円/坪は全国順位は293位です。前年からの変動率+0.11%は全国順位は384位となっています。
朝日町と同じ鉄道路線内で土地相場を比較すると、朝日町は近鉄名古屋線沿線の平均地価26万0703円/m2、JR関西本線沿線の平均地価24万0403円/m2を下回っています。近鉄名古屋線、JR関西本線の駅へ距離が短いほど朝日町の基準点地価は高い傾向にあります。
大紀町
- 地価平均:9210円/m2
- 坪単価平均:3万0446円/坪
大紀町の基準地価平均9210円/m2(2019年)、坪単価平均3万0446円/坪は全国順位は1439位です。前年からの変動率−2.75%は全国順位は1536位となっています。
大紀町と同じ鉄道路線内で土地相場を比較すると、大紀町はJR紀勢本線沿線の平均地価4万9586円/m2を下回っています。JR紀勢本線沿線の駅へ距離が短いほど大紀町の基準点地価は高い傾向にあります。
世界遺産のツヅラト峠がある大紀町は、三重県の中南部にあります。枝垂桜やつつじ山など、魅力的な自然が多い町です。他にも大内山動物園や錦向井ヶ浜遊パークトロピカルガーデンのように、家族で楽しめるスポットがいくつもあります。
南伊勢町
- 地価平均:1万0980円/m2
- 坪単価平均:3万6297円/坪
南伊勢町の基準地価平均1万0980円/m2(2019年)、坪単価平均3万6297円/坪は全国順位は1330位です。前年からの変動率−3.78%は全国順位は1663位となっています。
町の約6割が国立公園に指定されているのが特徴です。鯛やサバなどの漁業やミカン栽培などがあり、自然や伝統的技術を活かした「南伊勢ブランド」として事業を行っています。
度会町
- 地価平均:1万1437円/m2
- 坪単価平均:3万7809円/坪
度会町の基準地価平均1万1437円/m2(2019年)、坪単価平均3万7809円/坪は全国順位は1310位です。前年からの変動率−2.68%は全国順位は1519位となっています。
三重県内で2番目に小さな町で、自然に囲まれている度会町。駅や国道がない一方で、高速道路へアクセスしやすいのがポイントです。通勤や買い物などのアクセスがしやすく、公共バスや自家用車での移動が基本となります。
家を建てたことに対してかかってくる税金がある
土地を買ったり家を建てたりすると、さまざまな費用がかかります。費用を大きく分類すると、一度支払えば終わりになるものと、家や土地を持っている限り支払い続けなければならないものがあります。家を建てるときには、完成後にかかる費用を知っておかないと困ることにもなりかねません。
まず必要になるのは登記関係費用
家が完成したら1ヵ月以内に法務局が管理する帳簿に登録してもらう「登記」の申請をしなければいけません。
登記には、どんな建物なのかを登録する「表示登記」と、誰が所有者なのかを登録する「所有権保存登記」があります。登記をする場合には手数料として、「登録免許税」という国税がかかります。
家を建てるための土地を買った場合、その土地についても登記を行ったと思いますが、土地とは別に家の登記も行わなければなりません。また、登記を司法書士に代行してもらうと当然その報酬も必要です。
登録免許税の金額は、建てた家の課税標準額によって変わってきますが、最低でも30~50万円くらいはかかると考えておいたほうがよいでしょう。
不動産取得税にはさまざまな軽減措置も
家や土地を買ったときには、「不動産取得税」を支払わなければいけません。これは、不動産という高価な買い物をしたことに対する県税です。
家や土地を取得した日から60日以内に、県税事務所に申告書を提出します。この申告は、仲介業者や建築業者が代行していることも多いので、家の引き渡し時に確認してみましょう。
不動産取得税の金額は、その家や土地の固定資産評価額の3%です。固定資産評価額とは、市役所・町役場にある固定資産課税台帳に登録された不動産価格のこと。県が家屋調査を行い、国の決めた固定資産評価基準に従って価格を決定しています。
三重県では建物の用途や広さによって不動産取得税の軽減や減免を行っています。どのような軽減措置が受けられるのか、県税事務所に問い合わせてみましょう。
親からの資金援助で発生する贈与税
贈与税とは
贈与税は、個人から個人への財産受け渡しがある際に、受け取った側に課せられる税金です。親族かどうか等は問わず、「個人から財産を受け取ること」が対象となります。
ただし、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から「生活費や教育費」として受け取った場合は対象外となります。また、個人ではなく「法人から」受け取った場合も対象外です。ただ、この場合は所得税や法人税が課せられます。
ここで重要となるのが、「財産」の定義です。「財産」は現金に限らず、預金や土地、建物や株式、権利などなど、お金で見積もることが可能なものは、すべて財産とみなされます。
このことから、「親からは生活費や教育費の名目で受け取り、その後にそのお金で家を買えばいいだろう」という考えもあるかもしれません。ですが、国税庁のホームページには、いかなる名目で受け取っても「預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる」と明確に記載されています。名目上は生活費や教育費だとしても、贈与税がかかると考えておきましょう。
条件を満たしていると非課税となる
贈与税は親族も含め、人から財産をもらった時点でかかります。計算式は下記の通りです。
(年間で受けた贈与額-110万円)×税率-控除額(贈与額により変動)=税額
この式からも分かる通り、1年間に受け取った額が基礎控除額の110万円以内であれば、課税対象とはなりません。
また、住宅の購入、新築、増改築等をするために親や祖父母から資金を援助してもらう場合には「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できます。制度を利用すると、消費税8%の物件なら「最大1200万円」、消費税10%なら「最大3,000万円」の贈与までの贈与税が非課税となります。
さらにこの制度は基礎控除とは別に適用されるため、「消費税10%」の購入契約や新築・増改築の工事請負契約を結ぶ場合、最大3,000万円に110万円の基礎控除額を足した3,110万円の贈与までが非課税となるのがポイントです。
ただし、「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるには一定の条件があります。贈与された翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはなりません。非課税を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要がある点にも注意しましょう。もし申告をせず、後から贈与を受けたと発覚した場合、ペナルティを受けることになります。そうなってしまうと、住宅を建てる計画が上手く進められなくなるかもしれません。贈与があった際は、隠さず税務署に申告しましょう。
家を持っている限り払い続けなければならない固定資産税
家を所有していると毎年「固定資産税・都市計画税」という市町村税がかかってきます。毎年4月くらいに納税通知書が送られてくるので、記載されている期日までに納付します。
固定資産税・都市計画税は、固定資産評価額に税率をかけることで計算できます。税率は市町村によって多少の上下がありますが、固定資産税がおおむね1.4%、都市計画税が0.3%です。
ただし、新築住宅については固定資産税の軽減措置が受けられる場合も。どんな軽減が受けられるのか、受ける場合には申告が必要なのかなどは、市町村によって異なります。詳しくはお住まいの地域の市役所・町役場に問い合わせてみましょう。
税金以外にも、住宅にはさまざまな経費がかかる
安心のために保険に入る
家を持っていることでかかる費用は、税金やその手続きにまつわる経費だけではありません。毎年かかる経費として予定しておきたいのは、火災・地震保険費用です。
住宅ローンを利用した場合、ローン会社から火災・地震保険に入ることを義務づけられることも。そうでなくても、入っておけば万が一のときの安心につながります。
新築住宅でもいずれは修繕・補修費用がかかる
家を新築すると、これでもう一生涯安泰と思うかもしれません。しかし、ずっと住み続けていれば家も傷んできます。
風雨にさらされる外壁や屋根などは、10年に一度は塗り直しなどの補修をしたほうが長持ちします。その費用はだいたい100~200万円が相場です。
また、キッチンや浴室などの水回りも、15~20年で寿命を迎えます。もし水回りのフルリフォームをするとしたら、200~300万円は見込んでおいたほうがよいでしょう。
いざ補修が必要になったとき、予算がないからと時期を先延ばしにすると、家の資産価値はどんどん下がってしまいます。新築の時点から、あらかじめ修繕費用を積み立てておいたほうがよいでしょう。
当サイトでは、三重県で注文住宅を検討している方に向けて、口コミ評価が高い会社を、「デザイン」「自然素材」「性能」の3つの特徴別に分けてそれぞれ紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
デザイン・自然素材・性能に
それぞれ強みがある
三重県の注文住宅会社3選