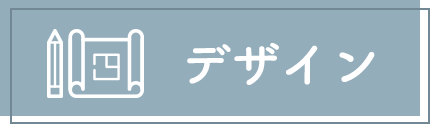はじめての注文住宅マニュアル
初めての家づくりのために、知っておきたい情報をまとめています。
注文住宅購入の流れ【三重県の場合】
大多数の方にとって注文住宅は一生に一度の大きな買い物です。
「失敗した」「こうすれば良かった」と思っても、やり直しはなかなか困難です。そうした失敗を防ぐためには、家づくりに関する知識を事前に得ることです。
まずは、注文住宅を購入し、建てるまでの流れについて。途中で失敗したと思っても、やり直せないことが多いので、どのような流れで進むのか、どこに注意すればいいのかをあらかじめ知っておくと安心です。一般的には、イメージ作り→見積もり→土地・施工会社探し→契約→建物のプランニング→契約→施工→入居という流れになります。土地探しや建物のプランニングでは、希望や譲れないポイントの優先順位をつけておくとスムーズです。
ここでは、注文住宅の流れとポイントについて説明します。
住まいのイメージ固め&スケジュールの把握
ご家族で住みたい家のイメージや望む暮らしのスタイルを話し合う時間を設けてみましょう。住宅情報誌やネットで建築事例などの写真をリサーチしながら行うと効果的です。
ここで大事なのが、ご家族全員でイメージを共有すること。その後の段取りをスムーズに進めるためにも重要です。
家づくりのスケジュールは依頼先や土地探し、建築プランの練り上げにどれだけ時間をかけるかで大きく変わってきます。
プラス工事開始から完成までは、木造2階建40坪程度で120日程度というのがひとつの目安です(※工法や業者などによって前後します)。
住宅展示場や現場見学会への参加
家づくりに限りませんが「現場」へ足を運ぶことは、大きなメリットが得られます。
例えば4LDKと文字だけで見るよりも、実際に建物に入り部屋の大きさや間取りなどを目で見て実感していれば、業者さんにより細かく的確な要望を出せます。足を運ぶ際は、デジカメかカメラ付きケータイ・スマートフォンをお忘れなく。注文住宅のプランを検討する際、貴重なヒントとして役立ちます。
建築現場見学・体験レポート
ここで、本サイトの管理人が参加した見学会のレポートを紹介させていただきます。私は家づくりを思い立って、住宅展示場などを回っていましたが、正直ピンとくるものがありませんでした。
そんなときに目にしたのが、「建築現場見学会」。同社では月1回ペースで、自社物件の建築現場を見学できるバスツアーを実施。しかも、施工担当者さんも同席で直接話を聞くことができると知り、申し込みました(参加者にお弁当が出る点にも惹かれました)。
当日は、まず基礎工事を行なっている現場へ。素人が普段見ることができない基礎の鉄筋やコンクリートの造形などを現場監督さん自ら説明してくれ、「強さ」へのこだわりを感じました。
特に、配筋の密集度を通常より狭くして強度を高めているというのは驚かされました。
建築途中の物件では、組立作業中の柱や梁、床材がどのように組み合わせて接合しているのかなどを、これも現場監督さん自ら、「実物」を使ってわかりやすく説明してくれました。私は社会科見学にきた子供のように、ワクワクして、聞き入ってしまいました。また、現場スタッフの皆さんの人柄や家づくりへの情熱といったものも、直接話しをすることで感じとることができました。
その後は、モデルハウスの見学もさせてもらいました。
見学会に参加して大きな収穫だったのは、参加者の皆さんと仲良くなれたこと。家づくりを検討している者同士、話も弾み、情報交換もできて有益でした。
仲良くなった方が別の日に参加した、同社の木材加工工場見学の様子なども教えてくれました。
見学会の後に、他社の見学会にも参加しましたが、多くはモデルルームや完成した後の物件しか見ることができませんでした。
建築途中の現場を包み隠さず見せてくれ、しかも現場スタッフさん自ら説明してくれるという、やり方に私はとても魅力を感じました。当初は、大手のハウスメーカーを考えていましたが、ここまでやってくれる姿勢に脱帽です。
土地探し
注文住宅用の土地探しは、決して簡単ではありません。ある調査によれば、情報収集開始から土地購入契約までの平均期間は14ヶ月と言われています。
ポイントはマメなリサーチにつきます。まずは不動産仲介会社を当たりましょう。
広告や雑誌、ポスターやチラシ、裁判所の競売物件や国有地払い下げの情報もチェックするとよいでしょう。
また、法律面では、建ペイ率や容積率(建築面積を制限する法律)、斜線制限(建物の高さを制限する法律)の有無など、法律的に住宅建設可能な条件をクリアしているかの確認も必要です。
資金計画
注文住宅を希望される多くの方は、住宅ローンを利用されると思います。
自己資金がどのくらいあり、いくら住宅資金に充てることができるのか検討してみましょう。
車の買い換え資金や1年分程度の生活費用などは、もしものときに備えて残しておくことがポイントです。
また、住宅ローンには色々なプランがありますので、内容をしっかり把握し比較検討したうえで、自分に1番合ったものを選ぶのが重要です。
銀行、信用金庫、JA、などの民間ローンや、住宅金融支援機構による「フラット35」や「すまいるパッケージ」などが代表格です。
安心して暮らせるバリアフリー住宅
注文住宅を建てる場合、合わないからといってすぐに引っ越すことはありません。何十年もその自宅で生活します。そこで、どの年齢の人にも使いやすいバリアフリーの環境を整えるのことも必要です。
段差をなくしフラットフロアに
自宅の中でケガが多い場所が段差です。各部屋の入り口などにできてしまう段差は、小さな子供やお年寄りがつまずきやすく、骨折してしまう危険性もあります。
特に、何十年も生活する自宅だからこそ、建てるときは問題なくても、後々暮らしにくくなる可能性があります。
そこで、階段以外の段差が現れないフラットフロアを選びましょう。フラットフロアにするメリットとして、ケガの防止だけでなく、杖や歩行器などを手軽に利用できることも挙げられます。場合によっては車椅子の使用もできるようにもなります。
さらに、掃除がしやすくなったり、洗濯物など重い物を運ぶのが楽になったりと、フラットフロアになるだけで動線が確保しやすくなるメリットもあります。いまや、フラットフロアは快適な生活には欠かせません。
また、フラットデザインにすることで、必ずしもドアじゃなくても良くなります。当たり前に使用しているドアは、引く場合に余分な移動が必要です。
そのため、フラットフロアに合わせて引き戸に変更してみましょう。手荷物があっても開けやすく、ドアを開かない分部屋を広く使えますので、今では引き戸のほうがメリットが多くなっています。
廊下・階段に手すりをつける
自宅の中で移動距離が長くなる廊下や、転落の可能性のある階段には、手すりをつけるのが効果的です。玄関や浴室などのどうしても段差ができてしまう部分に手すりを取り付けるのも良いでしょう。
手すりは力を込めるために必要ですが、身体のバランスを整えるためにも必要です。そのため、長い距離を歩くためにも手すりは必要となります。ただし、子供がいる場合、手すりの位置が低いと頭をぶつけやすくなるため、後回しにしても良いかもしれません。
さらに、手すりは金属製ではなく木材を使用していると、冬場なども快適に使用できるようになります。
また、階段は段差や勾配にも気を配っておきましょう。一段は低く、緩い勾配にすることで、年齢を重ねても上の階を活用できます。こうした階段に手すりがあると転落するリスクが格段に減りますので、階段には特にこだわりましょう。
玄関前にスロープをつける
注文住宅で見逃してしまうことが多いのが玄関前です。外観は変えられないことが多く、そのままにしてしまうことがあるのです。しかし、自宅へ入るためには必ず通らなければならず、移動が難しいと外出が億劫になってしまいます。
そこで、玄関前に階段がある場合は、スロープを設置しましょう。将来的に歩行器や車椅子を使用する場合にも、大いに活躍してくれます。段差を超えにくい小さい子供も移動が楽になりますのでオススメです。
ただし、この場合が併設するのがより効果的です。実は、スロープは上りやすい反面、下りる際には筋力が必要となります。そのため、下りるときには階段の方が使いやすい人も多いのです。また、スロープにも手すりがあると移動が楽になりますので、予算を踏まえて考慮しましょう。
細かなところのリスク回避
段差や手すりなどはメジャーなバリアフリーですが、他にも細かいところに気をつけることもバリアフリーには欠かせません。例えば、火事のリスクを回避するためにガスコンロからIHに変えたり、棚などを備え付けのものにして転倒のリスクをなくしたりすることも大切です。
また、照明関係も重要なポイントです。夜中にトイレなどへ行く際には廊下の照明をつけますが、スイッチまで遠いとそこまでの移動中に転倒するリスクがあります。そこで、人感センサーによる自動点灯にしたり、足元に誘導灯を設置したりするのもオススメです。
ただ、こうしたところのバリアフリー化は、建設後に変更することも可能です。初期費用を抑えるためには、後々自分でできることは外して、必要になるところからバリアフリー化を行うことも良いでしょう。
ユニバーサルデザインという考え方
バリアフリーと同じく重要視されているのが、ユニバーサルデザインという考え方です。誰にでも使いやすくするという点では同じですが、より多くの人が使いやすくなるようにするのがユニバーサルデザインの考え方です。
例えば、IHコンロにすることで高齢者でも安全に料理ができます。しかし、コンロの位置が左端になっていると、左利きの人には壁が邪魔で使いにくくなります。そこで、IHにするだけでなく、コンロの位置を真ん中にしたり、アイランド型にしたりすることで、誰にでも使いやすくなります。
実は、バリアフリーだけを行うと、必要としていない人には不便に感じることがあります。そのため、誰かに合わせるのではなく、生活している全員が使いやすくなるユニバーサルデザインを目指しましょう。
ハウスメーカーの選び方
見積もりや提案プランは要望通りか
当たり前の話ですが、注文住宅は施主の要望に応じて建てられるもの。
しかしながら、事前の打ち合わせや希望予算などに則した提示をしてこないような業者も存在しています。
もちろんその理由を問いただしてみるべきです。例えば、地盤改良のためなどの理由があったり、打ち合わせに基づく、業者からのより良い提案などであれば検討の余地は残されます。
逆に、自社の儲けを釣り上げるために行なってくる手合いは避けるべきです。
担当者は信頼のおける人物か
普段の窓口となる営業マンはもちろんのこと、設計者や施工担当者の人柄や誠実度などを推し量ることも重要です。
身だしなみや言葉づかい、マナーなどはもちろんのこと、プランに関する提案などに信頼性があるかなどをチェックしましょう。
例えば、マイナスやデメリットなどを包み隠さず話してくれたり、過去に手がけた建物に案内してくれるなどがあれば、ポイントは高いと言えるでしょう。
アフターフォローの体制はどうか
家というものは、建てて終わりでは無くむしろ建てた後が重要なので、どのようなアフターフォローをしてくれるかは大切なポイントです。
保証や定期点検の内容はもとより、なんらかのトラブルや不具合などがあったとき、すぐに駆けつけてくれるかといった点も重要になります。
注文住宅で気になる費用
注文住宅を建てる際に、もっとも気になるのが費用。すでに土地がある場合と、土地も一緒に購入する場合、それぞれの費用の相場や、収入別の予算相場について紹介しています。
不動産を取得すると「不動産取得税」が課せられますが、新築住宅の場合、この税金の軽減措置を受けることができるので、その条件などについても確認しておくといいでしょう。
住宅タイプ別に家造りの仕組みを解説
住宅のタイプによって、それぞれ特徴や仕組みが異なります。
構造体と内装・設備を分けて設計することで、高い耐震性をもちながら、何度でもリフォームができるというメリットのあるスケルトン・インフィル住宅、人もペットも快適に暮らすための間取りのアイデア、人気の輸入住宅の特徴とおもな種類、二世帯住宅の間取りの種類や、給付される補助金、軽減される税金などについてまとめています。
注文住宅のコストダウン
注文住宅を設計する上で悩みの種の1つとなりがちなのがコストの問題。それでも、構造をシンプルにする、施工面積を減らすなどの工夫によって、意図した設計を保ちつつコストダウンを実現する事も可能です。
ここでは、コストダウンにおける17のポイントをご紹介いたします。
三重県の地盤事情
三重県の地盤について紹介しています。大地震発生時には大きな被害が予想され、いざという時の地震対策・水害対策に備えるためにも、三重県の各エリアごとの地盤の強弱も把握してきましょう。地震に強い家を建てるためのポイントも解説しているので、三重県で住宅建築を考えている方は、参考にしてみてください。
三重県で治安のいいところ、悪いところ
三重県の治安についてまとめました。暮らしを考える前に、治安状況や犯罪への取り組みについて知っておくと生活を始めてからも安心のはず。三重県の治安状況や犯罪への取り組みについて解説しているので、犯罪が多いエリア・少ないエリアがどこなのかを把握し、安心安全な家づくりに役立ててください。